2025


【決勝】角田裕毅、トルクマップ修正要求。着々とマシンを自分好みに合わせ込むプロセスを進める【2025 Rd.4 BHR】
バーレーンGP決勝でレッドブルは苦戦を強いられながらも、2台ともにポジションを上げてマックス・フェルスタッペンが6位、角田裕毅は9位入賞を果たした。
角田はレース中にパワーユニットのトルクデリバリーについて不満を訴える場面もあったが、これは問題というよりもマシンを自分の好みに合わせ込んでいく過程のひとつだという。
こちらの記事は『F1LIFE』有料会員限定のコンテンツとなっています。
続きをご覧になるためには、ベーシック会員・プレミアム会員になって頂く必要があります。
(会員登録の方法はこちら)
※コース変更の場合は、旧コースの解除手続きを行なって下さい。
お客様の手で解除手続きを行なって頂かなければ継続課金は解除されませんのでご注意下さい。


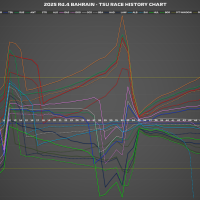







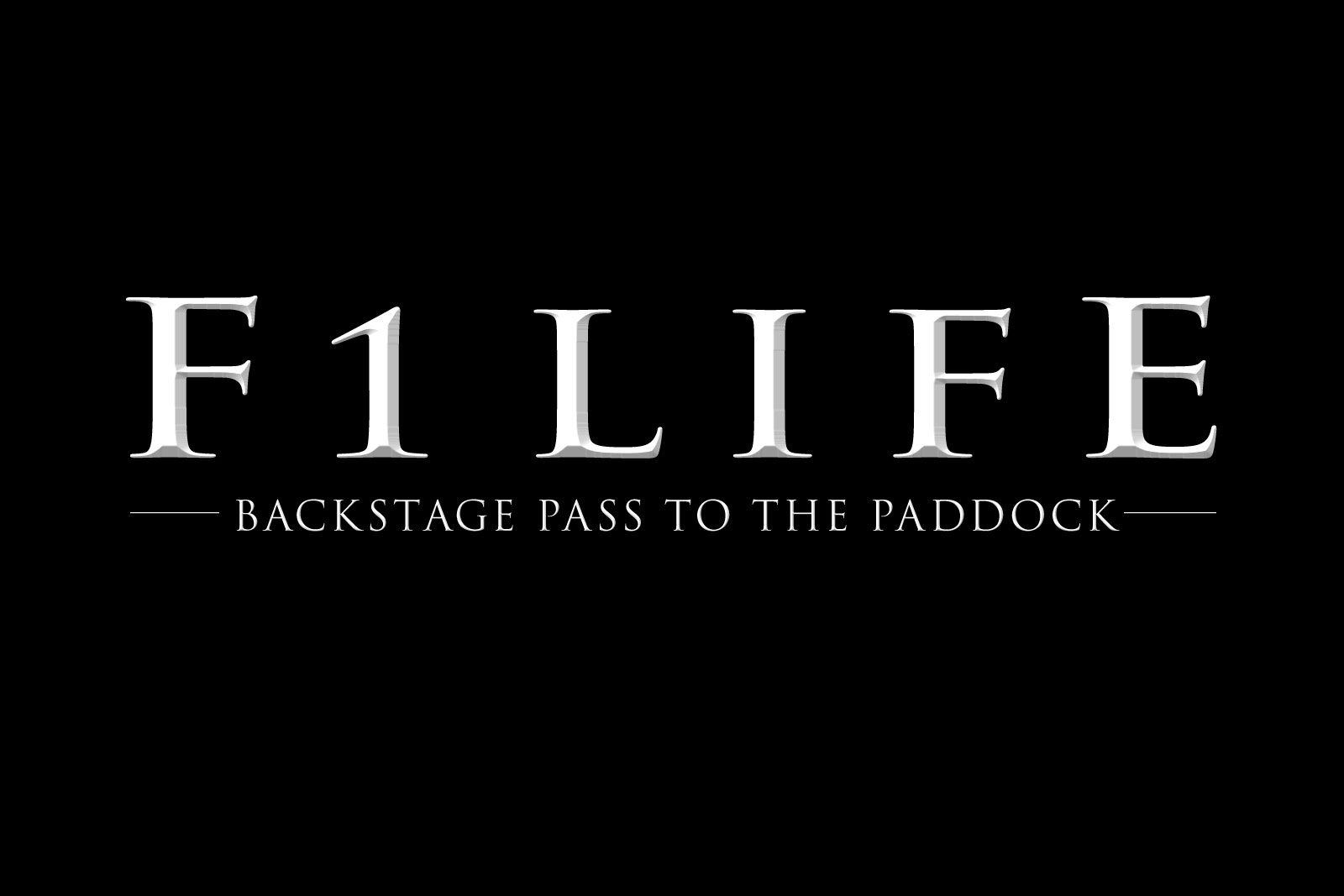
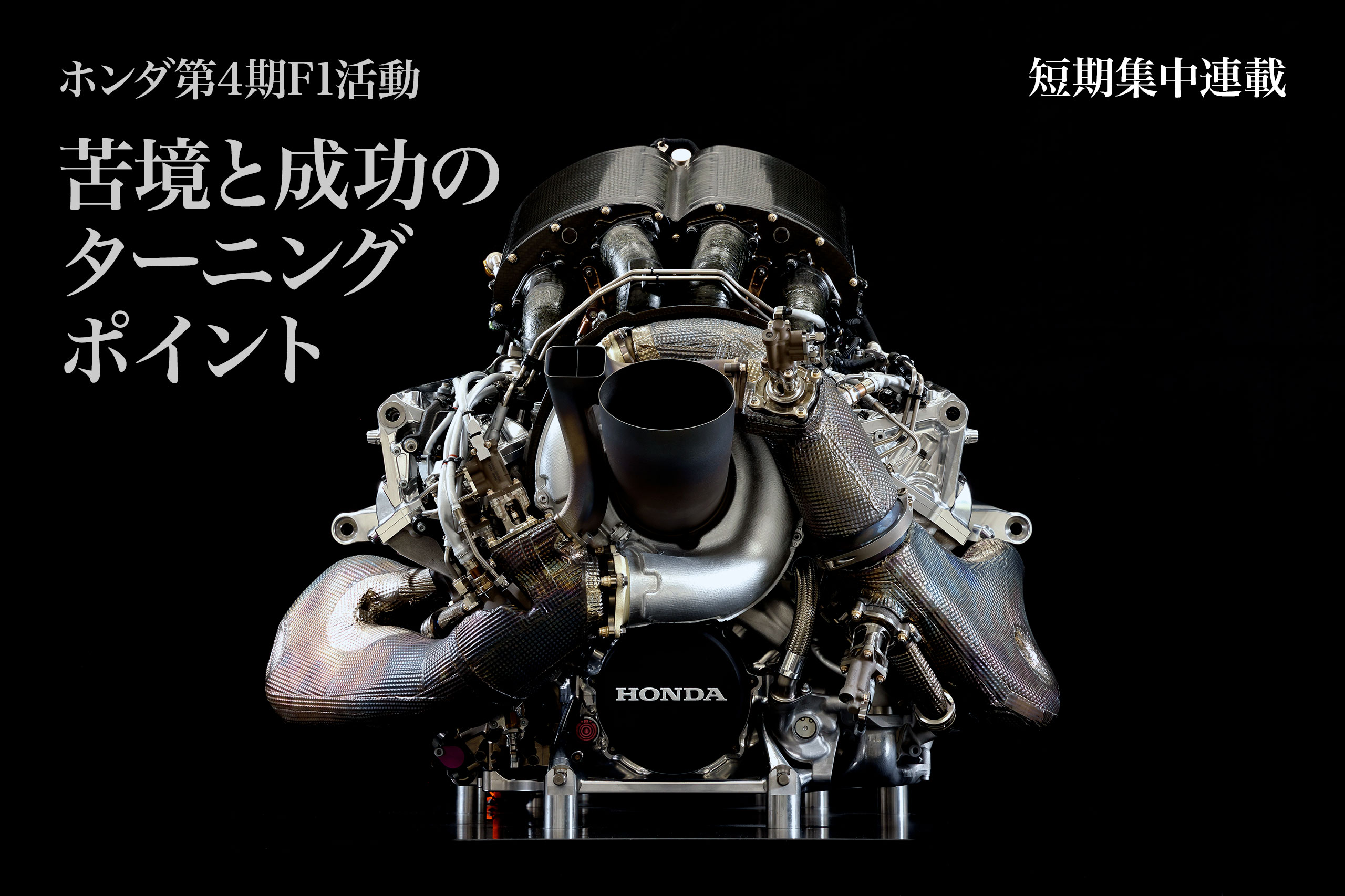

うーん、頼もしい!どんどんRB21を自分の手足のように扱えるようになって欲しい!
車体が落ち着いていればこういうアジャストももっとスムーズに進むんでしょうけど、TSU自身も急速に成長していくと思うので、そこにも期待ですね。
一言で「車にアジャストする(慣れる)」と言っても、感覚的な話だけではなく、このような様々な細かい設定・セットアップの微調整もあるんですね。とても勉強になります。
ハミルトンやサインツのような優秀なドライバーでも新チームのアジャストには時間がかかっている事を見ても分かるように、アジャストすることがいかに大変かつ時間のかかるプロセスかが分かりますね。そのような中で、たった2レースとはいえ、既に順応し始めているように見えるのは頼もしいところです。勝負はまだまだこれからですが、車の開発と平行して角田選手のアジャストが進んでいけば中盤戦くらいは良い勝負ができるようになるかもしれないので、期待しかありません!
HAMやSAIはPUメーカーが変わったのでさらに複雑ですし、それに比べるとTSUはマシン自体もかなり似たところがあるチーム間の移籍なので、シーズン中の急遽の昇格でもなんとかやれているということだと思います(ステアリング自体もモノとしては同じですし)。
アジャストそのものも素晴らしいですが、それに対峙する姿勢が素晴らしいなと感じます。「なんとかなるだろう」ではなくて、やるべきことはしっかりとやり、それでも簡単にいくわけじゃないから一歩ずつやるしかないという落ち着きが素晴らしいなと。
実践2戦目にして、車の根本的な部分へのアプローチが出来る状況になったんだなと思うのと同時に
はじめから、角田にしとけばこの時点でこんな事やってなかったのにって思いと、ホーナー勝ち馬にのるって言うか自身の選択ミスの取り繕いに必死だなって思ってしまいました。
こう言う情報はF1LIFEならではですね。
とても興味深いです。
細かいアジャストを同じチームで9年間し続けてきたドライバーと競い合うのがいかに大変なことかよくわかります。
ドライバーの才能がどうとか、クルマがピーキーだとか乗りやすいかどうかみたいな次元じゃないんですよね。1990年代くらいまではそういうマシンだったと思うけど、2000年代以降のF1マシンは電子制御バリバリで、要素があまりに多いですから。。。
角田くん、頼もしい限りですね!!!
着実にステップアップしてますね!
焦らず一歩一歩!
角田くん好みにアジャストしていけば、
トップ:10どころか、常連のトップ5争いになり、
その上の期待も膨らみますね!
F1LIFEでなければ分からない情報、
何時ありがとうございます
詰めていっていることもそうですが、自分から積極的に動く姿勢と、なおかつ焦らずひとつずつやろうという姿勢が成長を感じさせてくれますね。
トルクマップとペダルマップのお話は大変興味深く読ませて頂きました。今回は加速側の話でしたが、減速側にも同じような考え方でマップのようなものは存在するのでしょうか?
また、一般的には1レース(コース)に対してどの程度のマップ数が登録されているものなのでしょうか?ご存知でしたら教えてください!
20行目の「折原GMはおそらくトルクマップ側の問題だろうと見ている。」と25行目の「おそらくペダルマップの方ではないかと思います」がどう整合するのかよく分かりませんでした。トルクマップとペダルマップは異なるものというということではないのでしょうか。
おそらくお分かりかと思いますが(苦笑)、「ペダルマップ」の間違いでした(修正済み)。